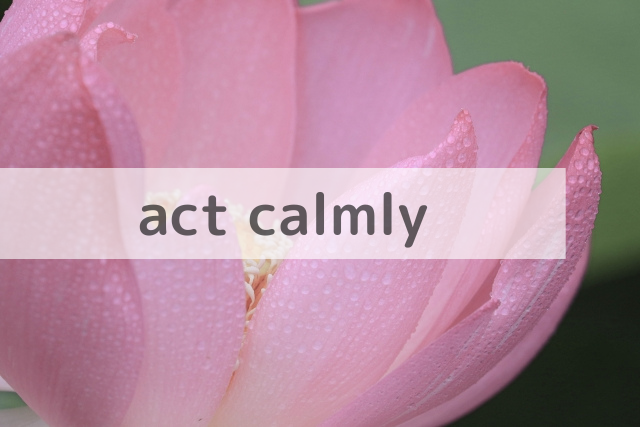森戸国次先生の絵が人気を集める理由について考えてみました。ネットの記事を読むと、分かりやすさがその理由の一つだという意見があります。その理由を語る前に、昔見た映画の話をしたいと思います。題名は忘れてしまいましたが、利休と豊臣秀吉の話です。秀吉は利休にお茶を誘われる場面が記憶に残っています。この話は美術史家でもあり、美術評論家・大原美術館館長、西洋美術振興財団理事長、東京大学名誉教授である高階秀爾氏の本から映画化されたものかは分かりませんが、その一部を紹介します。
「利休は自宅で珍しい朝顔を育て、近隣でその評判が高かった。豊臣秀吉はその評判を聞き、一度見てみたいと思い利休を訪ねた。利休は庭に咲く朝顔をすべて摘み取ってしまった。秀吉が訪れると、庭には一輪も花がないことに不満を示したが、利休に茶室に招かれると、そこには床の間に大倫の朝顔が一輪だけ活けられていて、秀吉の機嫌を直した。このエピソードは、日本人の美意識が華やかな装飾性を好む一方で、思い切って主要なもの以外を切り捨てる大胆さを物語っている。」
絵にも同じことが言えるでしょう。キャンパスに多くの絵画が描かれていると、一瞬は興味深いかもしれませんが、空間が制限されてしまうため、飽きてしまうことがあります。情報量が多すぎると、絵画が工芸品に見えることもあります。絵画は時間が経っても飽きない方が良いですよね。では、なぜ「飽きてしまう絵」と「いつまでも見ても飽きない」絵があるのでしょうか?
「飽きてしまう絵」は、キャンパスに情報が過多であり、視線がばらばらになってしまうことがあります。そのため、絵を描く人も見る人の感覚を考慮することが重要です。自己主張だけではなく、観察力も必要です。
絵を描く人は、自分が見たものが美しいと感じると、ついついそれを描きたくなるものです。色々な要素が美しいと思えるでしょう。「すべてを描きたい!」という気持ちはわかりますが、最初の直感を大切にしましょう。それがあなたの芸術の核心です。その瞬間にメモを取ることも有効です。
先生は背景にグラディエーションを多用していました。例えば、葉っぱの多い場所は、緑のグラディエーションを描くことで、葉っぱが具体的に描かれていなくても、見る人の心の中に一人一人異なる絵が描かれると思うのです。
ここで私の好きな方を紹介します。吉田博士版画家の作品です。アメリカで実際に行って描いてきた絵を話です。作品名「ヌー」小さい版画ですが絵は迫力がある絵でした。何十頭あるか分からない群れが、横切っている感じがする絵でした。でも良く数えてみると、3頭しかヌーが描いていないのです。描き方で迫力がこれほど違いが出るという話でした。
今回、キャンパスに沢山絵を描けば人が感動してくれるかという話でした。でも時と場合によっては、背景の余白に何か描かないとバランスが取れない事もあるので注意が必要です。